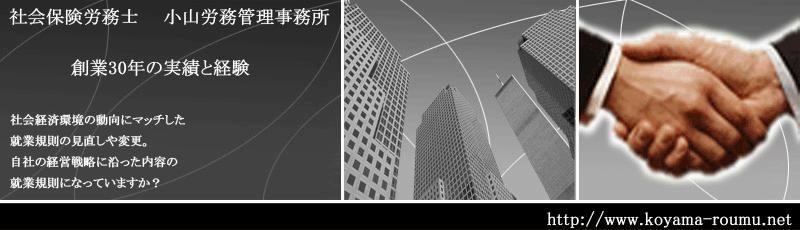特定社会保険労務士事務所とは
特定社会保険労務士とは司法制度改革で導入された一定範囲のADR代理権を持つ社会保険労務士(社労士)のことで、労使紛争の解決をお手伝いをします。
昨年「社会保険労務士法」が改正され、平成19年4月1日から「特定社会保険労務士制度」が始まりました。
特定社会保険労務士の必要性
特定社会保険労務士が必要となった理由は、個別労働紛争の増大にあります。
給与の不支給、残業代の不払い、年次有給休暇の未取得等、労働関係トラブル(個別労働紛争)が増え続けています。
それらを解決するために労働法令の専門家である社会保険労務士に対する新たな役割が求められるようになったのです。
特定社会保険労務士により行える業務
個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理業務に加え、新たに次の代理業務も行えるようになりました。
①個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
②男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
③個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理
社会保険労務士との違い
特定社会保険労務士は、労働関係トラブル解決のための知識を身につけた社会保険労務士のことです。
社会保険労務士との違いは「あっせん代理」ができることです。
つまり、当事者に代わってトラブル解決に係わることができる訳です
ADR(裁判外紛争解決手段)
裁判外紛争解決手続とは、ADR(Alternative Dispute Resolution)とも呼ばれますが、
仲裁・調停・あっせんなどの、裁判によらない紛争解決方法を広く指すものです。
例えば、裁判所において行われている民事調停や家事調停もこれに含まれますし、
行政機関(例えば建設工事紛争審査会、公害等調整委員会など)が行う仲裁・調停・あっせんの手続や、
弁護士会、社団法人その他の民間団体が行うこれらの手続も、すべて裁判外紛争解決手続に含まれます。
このような裁判外紛争解決手続を定義すれば、「訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、
公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」となります。