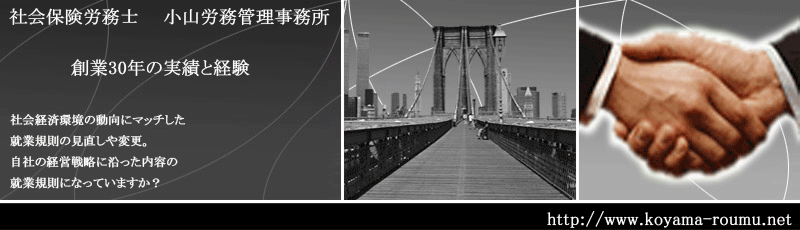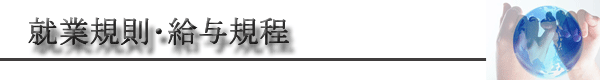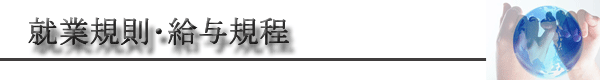
���A�ƋK���E���^�K���E�ސE���K���̍쐬�E�����E����
���ٗp�W�̊J�n����I���܂�
���֘A�@�K�̉����A�V�݂ɑΉ������������s���Ă��܂���
�@�@�J���_��@�E�p�[�g�^�C���J���@�ւ̑Ή�
���Љ�o�ϊ��̕ω����Ƃ̎���ɂ������쐬�^�p���s���Ă��܂���
�b�r�q�ɂ���g�D�����A�l���A�J�����s�E�E�E
����ƌo�c�ƏA�ƋK��
�@⇔�@�L���ւ̑Ή��@⇔�@�@�a�b�o����
����n�k�⊴���ǂ̗��s�A�e���Ȃǂ̍ЊQ�E�L���̍ۂ̊�@�Ǘ��̎�@�Ƃ��Ă��u���ƌp���v��v�i�a�b�o�j�A�Ɩ��ւ̉e�����ŏ����ɗ}���A���Ƃ̑����ĊJ�Ɏ������������\�z�ł��邩��Ƃ̊�@�Ǘ�������Ă��܂��B
�@��N�T���̎�Ő��V�^�C���t���G���U�̉e�����āA�V���ɑ���쐬������Ƃ������A�o���֎~�A����ҋ@�Ȃǂ̑���u�����܂����B
�@���Ő��V�^�C���t���G���U�̗��s�őz�肳��錇�⎩��ҋ@�ւ̋�̓I�Ή��Ȃǂ́A�܂��i��ł͂��Ȃ��悤�ł��B
�H���ŁA�p���f�~�b�N�A�������ӔC�E�E�E���Ђւ̎��O�K�v�ł��B
��E�������ȂǁA�]�ƈ���Ƒ��ւ̊����\�h��̎w���A�\�����[�����A���N�Ǘ��E�o�ދ̓K�ȊǗ��E�^�c�ȂǁA���A�s�������łȂ��A�n��ƂƂ��Ɋ�Ƃɂ����̑���u���邱�Ƃ����߂��Ă��܂��B
�����s�ł͒�����Ƃ��ЊQ�����ƌp���̂��߂̎菇�����쐬����ۂ̎x�����n�߂�B
�V�^�C���t���G���U�̗��s�ɂ���⇒
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/message03.pdf
�A�ƋK���Ƃ͉���
��Ƃœ��������ŘJ�g�̍Œ���̏A�Ə������߂����̂��A�ƋK���Ƃ����܂��B�������ߎ��A��Ƃ���芪���o�c�������ς��Ă���܂��B�l���ی�̎戵���A���a�Ȃǂ̃����^���w���X�A���[�N�V�F�A�����O�A��Ə��R�k�h�~�ȂǁE�E�E�B���̒��ɂ͗l�X�ȃ��X�N�����݂��A���O�ɗ\�����ĉ�����邽�߂̑�y�ю��ナ�X�N�ւ̑Ή���ȂǁA�܂��Ǝ�ƑԂɂ��Ή����ׂ��J���Ǘ����قȂ�܂��B�����ɉ����ʊ�Ƃ̎��ԂɑΉ��������e�L�������E���m�E�Ǘ����Ă����ׂ��ł��B
�ʘJ�g�������������Ă���A��ƌo�c����芪�����ɂ͗l�X�ȃ��X�N�����݂��A���O�ɗ\�����ĉ�����邽�߂̑�y�ю��ナ�X�N�w�b�W�ȂǁA�ً}���Ԃ𖢑R�ɖh�~����d�g�݂��\�z����K�v������܂��B
�����Q�Q�N�S���P����������J��@���{�s����܂����B�����ԘJ����}�����A�d���Ɛ����̒��a�̂Ƃꂽ���[�N����C�t��o�����X�Љ�̎�����ڎw���āA�J�����ԂɌW�鐧�x�̌����������s���܂����B���ԊO�J���̊����������������グ���܂����B
�A�ƋK���͊�Ƃ̌��S�Ȕ��W�̂��߂ɕK�v�s���Ȃ���
��Ƃ́A���̌o�c���O�ƌo�c���j�ɉ����ďA�ƃ��[�����쐬���A�]�ƈ��́A���̋K�������炵�A��ƖړI�̐��s�ɓw�͂���B
���s�̘J��@�ł́A�펞�P�O�l�ȏ�i�p�[�g�A�A���o�C�g���܂߂āj�g�p����g�p�҂́A�J�������̓��e���L�����A�ƋK�����쐬���A�]�ƈ���\�̈ӌ�����Y�t���ĘJ����ē��ւ̓͏o���`���t�����Ă��܂��B
���ԊO�J���ȂǘJ�g����̒����E�͏o���K�v�Ȃ��̂�����܂��B
���ۂɈӌ�������s��Ȃ�������A����I�ɍ쐬�����ӌ����⋦��͂͌���A�g���u���̌����ƂȂ�A�c��Ȏ��ԂƘJ�͂�v���邱�ƂƂȂ�A���ƌo�c�����Ɏx������������ʂƂȂ�܂��B
���Ղȍl�������ō쐬�A�͏o���邱�Ƃ͋֕��ł��B
�܂��A���Ƃ��P�O�l�����ł����Ă��ό`�J�����Ԑ��A�ٗʘJ�����A�N��Ȃǂ��̗p�����A�Ə����ł���A�������肵���A�Ə������߂��A�ƋK�����K�v�ƂȂ�܂��B
�Ǘ��E�Ǝc�Ǝ蓖
�J��@�ł́u�ēႵ���͊Ǘ��̒n�ʂɂ���҂ɂ͘J�����ԁA�x�e�y�ыx���Ɋւ���K��͓K�p���Ȃ��v�ƒ�߂Ă��܂��B�i�A���A�[��Ƌy�єN�x�Ɋւ��Ă͓K�p����邱�ƂɂȂ�j
�Ǘ��ē҂͈̔͂ɂ��Ă͏��a�Q�Q�N�̍s���ʒB�╽���X�N�̍ٔ���Ɏ�����Ă��邪�A�Ǘ��ē҂ɊY�����邩�ۂ���
�@�@�@�o�c�҂ƈ�̓I�ȗ���ɂ��邩�ǂ���
�@�A�@����̋Ζ��Ɏ��ԊǗ����Ă��邩�ǂ���
�@�B�@���̒n�ʂɑ��ĉ��炩�̓��ʋ��^���x�����Ă��邩�ǂ���
�ȏ�R�_�𑍍̏����Ζ��̎��Ԃɑ����Ĕ��f����邱�ƂɂȂ�܂��B
�]���̔�������݂�ƁA�Ǘ��ēҐ��͗e�Ղɂ͔F�߂��Ȃ��X���ɂ���܂��B
�����Q�O�N�P���Q�W���̃}�b�N�̔����ł��������Ƃ������Ă��܂��B
����ł͂ǂ�������悢�̂��H
�E���x�ύX����̂��H
�E�ߋ����͂ǂ�����̂��H
�E���Z����̂��H
�E���k�ɂ���̂��H
�E�ٔ��ɂ���̂��H
�E�T�i����̂��H
�E�E�����������炵�Ďc�Ǝ蓖�̎x���Ώێ҂ɂ���̂��H
�E�c�Ƃ�t������@�͂ǂ�����̂��H
������Ǘ��E��ւ̂����k�������Ă��Ă���܂��B
�ē�����̐�����������O�ɑΉ�����u���Ēu���܂��傤�B
�����X�ܓW�J���鏬���ƁA���H�Ɠ��̓X�܂ɂ�����Ǘ��ē҂͈̔͂̓K�����ɂ��ā`��̓I�Ȕ��f�v�f�������ʒB�`�yPDF�z
������@�Ǘ��ē҂ɂ��Ă̂p���`
�A�ƋK���ƘJ���_��
�A�ƋK���̖@�K���̗��j�Ɛ���
�A�ƋK���ƌ��s�J��@
�J���_��@���ƏA�ƋK��
�A�ƌ`�Ԃ̑��l���ƏA�ƋK��
�����K���E�ސE���K��
�A�ƋK���ƘJ���_��
�u�A�ƋK���v�Ɓu�J���_��v�Ƃ͍��{�I�ɈقȂ�ʌ̖@���x�ł���B
�J��@�Q���Q�����A�J�g�o���ɘJ������A�J���_��ƕ���ŏA�ƋK���̏���`���A�������s�`�������A�s�����ǂ��A�J��@�P�T���̘J�����������`���ɂ����u�����v�͏A�ƋK���̖����ő����Ƃ̒ʒB���Ă��邱�Ƃ�(���a�Q�X�E�U�E�Q�X��R�T�T��)�A�ƋK���̘J�������ݒ肪�@���x��̂���ł��邩�̂悤�Ȉ�ۂ�^���Ă���B ���s�̘J��@�E�A�ƋK���@���ɂ����Ắ@�A�ƋK���ƘJ���_��@�͘J�������̐ݒ�ƓW�J�ɍۂ��āA����̋@�\���͂������̂Ǝ~�߂��A�A�ƋK���ƘJ���_��͎��ԂƂ��č��������ɂ���Ƃ�����B
�A�ƋK���ɂ��Ă̖@�I�����_�ɂ́A�@�K�͐��A�_����y�ю����K�͐��Ȃǂ�����A���ꂼ��̗���ɗ����Ⴊ�݂��邪�A�H�k�o�X��������(���a�S�R�N�P�Q���ō��ّ�@��)�ŁA�ʓI�ȘJ���_��ɂ�����J�������̌���́A���̏A�ƋK���ɂ��Ƃ����������銵�K���������Ă�����̂Ƃ��āA���̎Љ�I�K�͂Ƃ��Ă̐�����L���邾���łȂ��A���ꂪ�����I�ȘJ���������߂Ă������A�@�I�K�͐����F�߂���Ƃ��Ă���B
�� �y�[�W�g�b�v
�A�ƋK���̖@�K���̗��j�Ɛ���
���������̏A�ƋK���E�E�E���{���B�Y���Ƃ̍����̂��ƂɊJ�݂������c�H��ɂ́A�W�c�I�ٗp�Ǘ��̎�i�Ƃ��Ă̏A�Ƃ̒����ƋK�������炳���邽�߂̖��ߋK�����������B
�����R�P�i�P�W�X�W�j�N�A�u�E�H�K���v�����グ��ꂽ���A�A�ƋK���ɂ��K���͌ٗp�W�����݂��Ȃ����߂ɁA���R�T�i�P�X�O�Q�j�N�̍H��@�Ăł͏A�ƋK���K���͒f�O���ꂽ�B
���̌�A���S�S(�P�X�P�P)�N�H��@�����肳�ꂽ���A�ƋK���K���͑吳�P�T�i�P�X�Q�U�j�N�����H��@�{�s�߂ɂ���Ď������ꂽ�B����炪���s�J��@�Ɉ����p����Ă���B
�吳�P�T�N�@���́A�u�E�H�m�A�ƃj�փX���������V�j�փX���K���m���e�����j�V�e�V���E�H�j���m�Z�V���H���ƃm�i�s�m�~�������Z���g�X�����m�v(�H��@�{�s��)�܂�A�Ə����A�K�������m�������A�ƋK���̍쐬���`���t���A�s�������ւ̓͏o�A�ύX���߂̂��Ƃɂ��̓��e�̓K������}��Ƃ������̂������B
�� �y�[�W�g�b�v
�A�ƋK���ƌ��s�J��@
���a�Q�Q�i�P�X�S�V�j�N����̌��s�J��@�́A�펞�P�O�l�ȏ�̘J���҂��g�p����g�p�҂ɁA�J�����Ԑ��x�A�����̌���A�v�Z���@�A�ސE�Ɋւ��鎖�����̏W�c�I�A����I�ȘJ���������e�L����A�ƋK���̍쐬���������ċ`���t���Ă���B�i�W�X���A�P�Q�O���j
�V���Ɏg�p�҂ɏA�ƋK���쐬�E�ύX���̉ߔ����J���ґ�\�̈ӌ�����`�����ۂ�(�X�O��)�A�J���_��ɑ���Œ�J�������ۏ�I���͂��K�肵���B(�X�R��)
���̖ړI�E��|�͂Ȃ�ł������̂��B��ʓI�ɂ́A�J�������̋q�ω��E���m���ɂ��J���җ��v�i��̂��߂́A�J�g�̎��I����⇒�_��W�ւ̍��Ƃɂ��㌩�I����̂��߂̖@�V�X�e���Ƃ����悤�B
�@���J����������̊�{�����͘J�g�Γ����茴���i�Q���P���j
�� �y�[�W�g�b�v
�J���_��@���ƏA�ƋK��
�ߎ��A�A�ƌ`�Ԃ̑��l���ɂ��ٗp�E�J���W����芪���̕ω��ɔ����A�J�������̏��O���[�v����J�������̕ύX�̑����������邪�A���قɌW�镴��������������ɌW�镴�����n�ߌʘJ���W�������������Ă���B
�����Q�O�N�R���P���Ɏ{�s���ꂽ�u�J���_��@�v�ł́A�]�܂����J���_��̘J�g�̂���������Ǝ�ƘJ���҂̑o���Ɏ��m���A�~�����K���ȘJ�g�W���\�z���A�����𖢑R�ɖh�����Ƃ��Ă���B
���̊�{�I�l�����́A�A�ƋK�����߂��郋�[�����m�ɂ��邱��
1.�@�A�ƋK���ƌʘJ���_��̊W�̖��m���@�i���Ӑ����̐���̕K�v�j
2.�@�A�ƋK����ύX����ۂ̃��[���̖��m���@�i�ύX�̍��Ӑ����̐���̕K�v�j
3.�@�A�ƋK���̕K�v�L�ڎ����̒lj��@�i�]�����z�]�E�o���A�x�E�E�������R���j
4.�@�_��������̖��������̒lj��@�i�]�����z�]�E�o���j���ʂɂ�閾�����@
5.�@�̗p�������C���p���Ԓ��̉��قւ̃��[���K�p
6.�@�������̍����@(���p�@���̐ݒ�)
7.�@���̑��J���_��I����ʂł̃��[���̖��m���@�i���فA���ق̋��K�I�������j
�� �y�[�W�g�b�v
�A�ƌ`�Ԃ̑��l���ƏA�ƋK��
�A�ƌ`�Ԃ̑��l���ɔ����A���K�ٗp�̊������ቺ���A�p�[�g�A�A���o�C�g�A�h���J���ҁA�_��Ј��A�����Ј��ȂǗl�X�Ȗ��̂����K�ٗp���������Ă���B ���ɁA�T�R�T���Ԉȏ�̃t���^�C���҂ƕω��Ȃ��K�̏]�ƈ����������Ă���(�h���E�_��E����)�B �����Ƃɂ����鐿���J���҂Ƃ��Ă̏]���҂��������Ă���B �K�ٗp�ɂ��R�X�g�}������Ǝ��v�ɍv�����Ă���B�K�p�͈͂��敪�����K��̍쐬���d�v�ł���B
�� �y�[�W�g�b�v
�����K���E�ސE���K��
�J��@89���ɂ́u�����̌���A�v�Z�y�юx�����̕��@�A�����̒���y�юx�����̎������тɏ����Ɋւ��鎖���v�ɂ��č쐬���A�ύX�����ꍇ�ɂ����Ă��s�������ɓ͏o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���B���A���@11���ɂ́u�����Ƃ́A�����A�����A�蓖�A�ܗ^���̑����̂̔@�����킸�A�J���̑Ώ��Ƃ��Ďg�p�҂��J���҂Ɏx�������ׂĂ̂��̂������v �ƒ�`���Ă���A�A�ƋK���A�J���_��A�J������ɂ��A�\�ߎx�����������m�ł���ꍇ�̑ސE�蓖�������ł���B
1980�N��̉~�n�����u�\�͎�`�v�������x�ɑ��A90�N��ȍ~�o�ϊ��̌��ς�����{�̒������x�́u���ʎ�`�v�������x���Nj�����Ă����B�\�͂Ɛ��ʂ͈��ʊW�������Ċ�Ƃ͏]�ƈ��̔\�͊J����}��A�\�͂����p���Ȃ���u���ʁv���グ�Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
�v��ƁA�E�����s�\�́i�E�\���i�����j�������(��������)�ւƕω������B�d���̌��ʂ�]�����Ďx����������ł���B
���l�������A�ƌ`�ԂɑΉ������A�ƋK���A�����K���̓K�p��_��ȉ^�p�����߂���B
�������N��Ҍٗp����@�ɂ��A��N�N��̈����グ�A�p���ٗp���x�̓�����Čٗp�_��A�K�i�N��������N������̔p�~�A�V��ƔN�����x�̗̍p�Ȃǂɂ��ސE�����x�A�J�������̉����A�艺���ȂNJ�ƌo�c����芪���ۑ�͎R�ς��Ă���B�ߋ��̔����]���E�ᖡ���č��x�̕K�v���A��������L���A���K�v�Ȏ菇�S���͂���������A�ƋK��������K��̉������̐S�ł���B
�ސE�����x���N���I�Ȃ��̂���\�͎�`��ʎ�`���x�̑ސE�����x�Ɉڍs���ׂ��ł��낤�B
�� �y�[�W�g�b�v